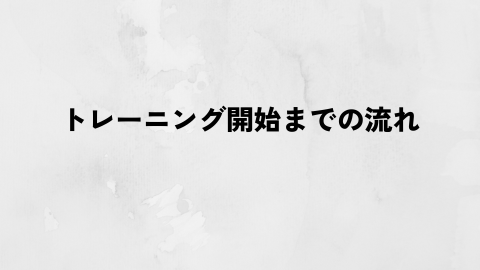奈良県香芝市のパーソナルジムENRICH GYM 香芝の須田雅人です。
今回は、夏バテ(Heat Stroke)について解説します。
夏バテは一般的には、夏場の全身の倦怠感・無気力・イライラ・食欲不振・不眠・ふらつき・疲労といった体調不良全般を指します。
目次
夏バテの症状
特に身体の調節機能が未熟な幼児は、脱水症状が起こりやすくなります。
お年寄りは体温が上がって熱中症(日射病と熱射病)を起こしやすいので注意です。
1全身のだるさと疲労感・無気力
夏バテの代表的な症状である全身のだるさと疲労感。何となく体がだるく、疲労がとれない日が続きます。
2食欲不振
自立神経の不調で食欲が低下し、消化器機能が低下すると、エネルギーや微量栄養素(ビタミン・峰れる)の不足を招きます。
それによりだるさや疲労感が増してきます。
食欲のない夏は、冷たい麺類やジュース、アイスなど糖質過多(とくに生成された糖質、糖分)になります。糖質をエネルギーに変換するビタミンB1が不足しがちになり、活動や回復のためのエネルギーが作られず疲労感が増します。
3胃腸障害
冷房にあたり過ぎたり、冷たい飲食物を多く摂ると胃腸が冷えて、機能低下が起こります。
下痢や便秘を起こしやすくなります。食欲不振で食事量がへると、腸の動きが不活発になり便秘を引き起こします。
4体重減少
食事量低下は、筋肉量低下を招き体重減少に繋がります。筋肉量が減れば身体の重さをより感じやすくなったり、食事量が増える冬に太りやすくなります。
5むくみ
冷房の効いた部屋に長時間いたり、冷たいものを多飲すると血流が低下し、水分代謝が十分に働かずむくみやすいです。
6ストレス
外と室内での寒暖差ストレスで、イライラすることがあります。イライラ対策には、温度・湿度・服装・風向きを調整する必要があります。
7めまい・たちくらみ
めまい・立ちくらみは多量の発汗により脳への血流が一時的に減ることで起こります。
暑さで体温上昇すると、体温を下げようとして血管が広がります(血管拡張)。血管拡張すると血圧低下し脳に届く血液が少なくなり、ふらつきなどの症状が出るのがめまいのメカニズムです。
8頭痛
冷房の効いた部屋に長時間いると、肩や首の筋肉が緊張し血行悪化し、頭痛が起こります。
また、発汗で水分を失い脱水症状になりやすく血流が低下し頭痛を引き起こしやすくなります。
9免疫力の低下
夏バテの原因
自律神経の乱れが夏バテの主な原因です。自律神経系は、内分泌系・免疫系と共に体内恒常性(ホメオスタシス)を支配しています。
1熱帯夜による睡眠不足
地球温暖化やヒートアイランド現象によって、夜間の最低気温が25℃以上の熱帯夜が増加しています。
体温が下がらないと副交感神経が優位になりづらく睡眠障害になる可能性もあります。睡眠によって日中の疲労を回復できず、自律神経の乱れから夏バテになります。
就寝中にでる成長ホルモンが疲労回復を促すため、睡眠障害により疲労回復できずだるさを感じます。
2高温多湿な環境による発汗異常
人間の身体は、汗をかいて蒸発するときに身体の熱を奪って体温調節をしていきます。しかし、高温多湿な環境では汗の蒸発ができず、体内に熱がこもり易く夏バテ症状が起こりえます。
発汗自体はよいことですが、大量にかきすぎると水分とミネラル不足によって脱水症状を引き起こすので注意です。
3糖質の過剰摂取
4水分不足による脱水
5冷たい飲食物の過剰摂取
夏バテのメカニズム
身体は自律神経の働きによって、暑さを感じると発汗して熱を放散し、体温を一定に保ちます。
しかし、

-11.png)